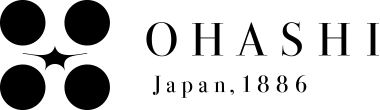SDGs食器の取り組み事例のご紹介
近年では様々な要因から食器を作るために必要な原材料の枯渇や高騰が進んでいます。
そのような中で持続可能な社会の実現に向け、モノづくりにおいても
「SDGs」という考え方が大きな注目を集めています。
大橋洋食器では、お客様と一緒にこのような課題に対して何ができるかを考え、
食品廃棄物などを利用した製品の開発に取り組んでいます。

茶殻から生まれた新しい「Re:シリーズ」、Re:Green tea
縦に長い新潟県の中でも東北、山形県寄りに位置する村上市。
余すことなく食べる伝統的な食習慣から「鮭」のイメージが強いこの街ですが、
実は江戸時代初期からチャノキの栽培が行われており、「北限の茶処*」とも呼ばれます。
※営利産地としての北限
一般的に茶処というと静岡や三重などの温暖な地域のイメージがありますが、
秋冬の木であるツバキやサザンカの仲間ということもあり、寒冷地でもチャノキの栽培を
行うことができます。(産地として有名な京都の宇治市も厳冬の地と言えます)
また、雪国ならでは利点として、日照時間が少ないことから渋みの元であるタンニンが出にくく、
旨味や香りが立ちやすいことが挙げられ、根強い人気を誇ります。

始まりは、お茶農家の「端材」という課題
最初のきっかけは、とあるイベントでの偶然の出会った、
明治元年創業、村上茶の老舗である北精園茶舗様から伺った
「緑茶を加工する際に、大量の端材が出てしまう」というお話でした。
あまり知られていませんが、茶葉の中でも煎茶になる部分というのは限られていて、
その他の茎や芽などの部分は“出物”と呼ばれ、別物として扱われるのだそう。
この“出物”はさらに茎茶や粉茶などの副産物に分けられた後、再利用できない部分が
廃棄されます。
それでも大切に育てた茶葉を捨てることなく、新たな形での使い道を模索したい
という思いから始まったのが、新たな「Re:」シリーズである「Re:Green tea」の
開発プロジェクトでした。
製品化への挑戦:加工のしにくさと発色の壁
同じ飲料由来であるコーヒーの事例があったので、同じスキームで問題ないと
考えていましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。
食器の原料として安定的に加工していくためには非常に高度な技術を要します。
例えば、色。
「茶色」と言って一般的に思い浮かべるのが、いわゆるブラウンであるように
天然物由来だと色味が安定せず、グリーンともブラウンとも付かない曖昧な色味に
なる場合があり、この定量化がまずは課題となりました。
また、茶器へのアップサイクルが目標だったので、せっかくのお茶の色が器に埋没
してしまう、という点も課題になりました。
お茶らしいグリーンが出せるように調整を重ね、最終的にブラウンとグリーンが
深みのある色味が出せるように。
後者の課題は見込みの部分に白釉を掛ける「塗分け」を行うことで解決しました。
課題を乗り越え、いよいよ販売を開始
そうした種々の課題を乗り越え、完成したのが「Re:Green Tea」の湯呑み。
外側で緑茶本来の美しいグリーンを基調にした独特な風合いを表現し、内側は
クライアントの「お茶の色が映えるようにしたい」というオーダーを叶えるべく
お茶の色を引き立てる白色を合わせた、機能性とデザイン性を両立したプロダクト
になりました。
こうしてできたアイテムは単なる「湯呑み」という製品でなく、お茶農家の方の大切な
茶葉を余すことなく活かしたいという願いと、少しでもお茶農家の方の課題を解決の
一助になりたいという私たちの想いが込められた思い入れのある一品になりました。
幸いなことに、このストーリーに共感してくださり、発売以来大変好評をいただける
までになりました。
「廃棄物」で終わらせない、新たな付加価値と循環型社会のために
今回の例のように、「何気なく廃棄をしているけど、何かに使えないのだろうか」と思う食品廃棄物が
ございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
お店や事業所で実際に出た食品廃棄物のアップサイクルで、御社のブランドストーリーに付加価値を
加えたり、SDGsへの参画による社会的なスタンスを示すアイコン作りのお手伝いができるかもしれません。
私たちもこの活動を通じ、皆様と共に循環の輪を少しずつ広げるお役に立てれば幸いです。
ご興味がありましたら、こちらの記事も宜しければご覧ください。
本記事に関するご連絡は以下までお願いいたします。
https://www.ohashi-web.co.jp/contact/